ビジョン・ミッション・バリューの浸透取り組み14.6%!
組織と仕組みづくりパートナー/中小企業診断士の蛯原健治です。
社長がいちいち言わなくても、社員が勝手に動いて利益が2倍になる組織作りのコツをお届けします。
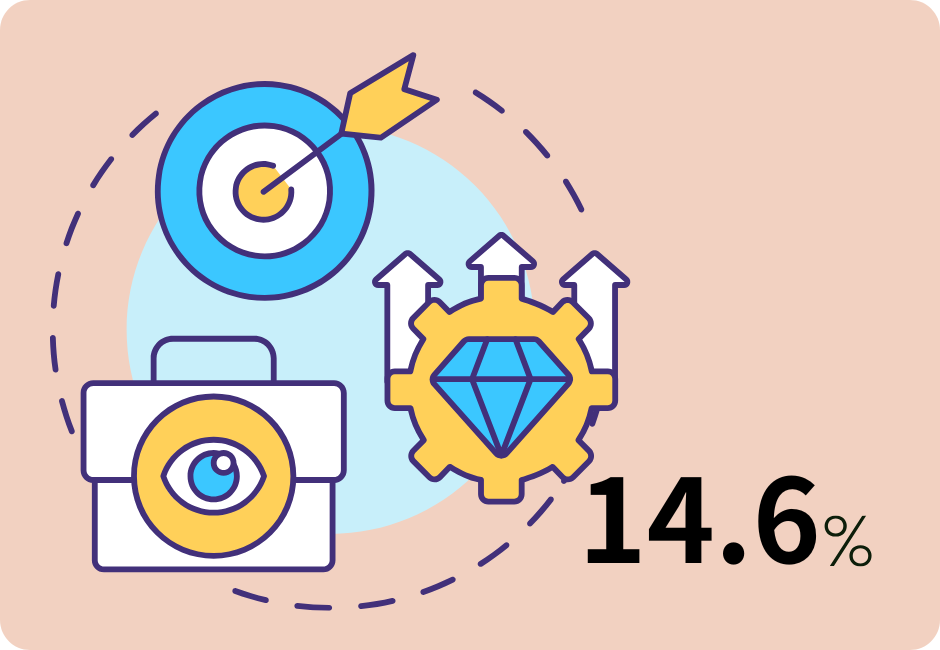
-2021年12月の中小企業経営者対象調査-
ミッション・ビジョン・バリューを策定しているのは28.6%
そのうち、社員に浸透させるための取り組みを行っているのは50%であり、
10%は「何もしていない」
36.7%が「自社サイト/採用サイトに反映しているのみ」
でした。
\戦略人事第三弾/
サクセッションプランを作成したら
次は何をやるのかといえば
ビジョン・ミッション・バリューの再考です。
ここでいうビジョンは、
5年後ではなく、
もっと時間軸が長いスパンで考えたものです。
自社が貢献し創り上げたい世界という大きなものです。
ミッションは、
2代目や3代目など後継者がしっくりこない場合は、
ミッションの解釈や言葉を変えるのもありかと私は思います。
バリューは、
ビジネスモデルに合わせて変えるものです。
ビジネスモデルが変化すれば、
バリューも変化させることで
社員の行動が変わります。
ここでするどい読者の方は気づいたと思いますが
事業を複数持ち運営している企業は
事業ごとの
ミッション・ビジョン・バリューの策定
が必要です。
ビジネスモデルにあわせる必要があるからです。
そもそも、各事業はそれぞれ
市場・顧客・競合・提供価値 が異なります。
事業単位でミッションを定義することで、
「なぜこの事業が存在するのか」
「顧客にどんな独自の価値を届けるのか」
が明確になり、
社員や顧客に伝わりやすくなります。
会社のビジョン(10年後以上の長期の理想像)は共通でも、
各事業がそこにどう貢献するかは異なります。
事業ごとのビジョンを持つことで、
「この事業は3年後にどんなポジションにいるか」
「どんな顧客課題を解決しているか」
が描け、
経営資源の配分や戦略投資の判断がしやすくなります。
全社共通のバリューはあっても、
事業の特性により求められる行動基準は違います。
例)
製造事業 →「品質第一」「安全を最優先」
小売事業 →「スピード対応」「顧客体験を重視」
事業単位でバリューを定めることで、
社員が日々の判断を下しやすくなり、
顧客に対する一貫性あるサービス提供につながります。
また、従業員にとっても
「この事業で働く意味」が具体的になり、
モチベーションが高まります。
今日は、中小企業の戦略人事第三弾
ビジョン・ミッション・バリューの再考についてでした。
皆さんも会社全体、事業単位毎に
ビジョン・ミッション・バリュー
を再考してみませんか?
【えびマガ】登録はこちらから
社長がいちいち言わなくても、社員が勝手に動いて利益が2倍になる組織作りのコツが分かるメールマガジン

